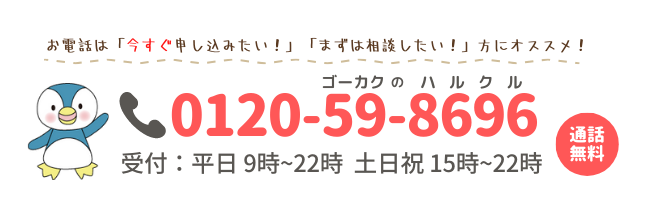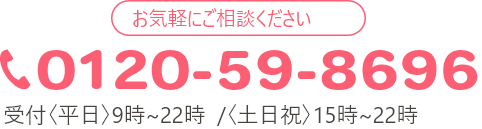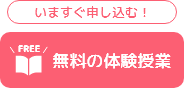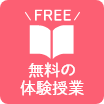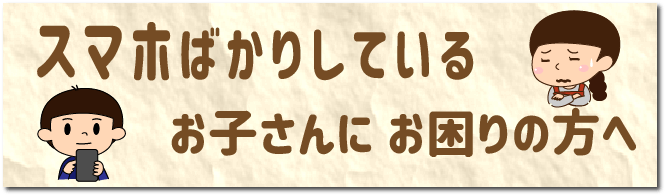
「スマホを与えた瞬間、成績がガクッと下がった」
「スマホ使用の問題で親子ゲンカが絶えない」
私たちえーるは、26年間11,183人のお悩み解決してきましたが、ここ数年で、「お子さんのスマホに関するご相談」が急増しています。ほとんどの中学生が持っている、と言っても過言ではないスマホですが、便利な半面、学力低下という問題を引き起こしやすいツールでもあります。スマホが、お子さんたちに大きく影響を与えているのはなぜでしょう?
この記事では、スマホに関するお悩みや、科学的な根拠、子どもが上手にスマホと付き合う方法まで、詳しくご紹介します。
子どものスマホ問題、深刻な学力低下とどう向き合う?
「YouTubeで夜更かしばかりして、朝起きてこない」
「勉強は後回し、ゲームがなかなか終わらない」
「食事の時間以外はずっとスマホを触る」
私たちえーるへのご相談では、このように、スマホが原因で親御さんの悩みが深刻化しています。「みんな持ってる」「学校の連絡で必要だから」と言われ、与えた途端に、成績が急降下した。 こんなお話は珍しくありません。
その他、夜更かしの原因になり翌日の授業で居眠りをしたり、朝起きれなくなって、最悪の場合不登校になる子もいます。
よくあるスマホ関連のお悩みトップ3!お子さんはどうですか?
私たちえーるに多く寄せられる、「子どものスマホに関するお悩み」をランキング形式でご紹介します。
1位 時間があればスマホばかり!勉強が手につかない
- 勉強しているはずの部屋を覗くとスマホでゲームをしていた
- テスト前なのにYouTubeやTikTokを見ていてビックリ!
- 親子ゲンカのもとは、いつもスマホの使用時間のこと
2位 スマホを与えた途端、成績が急降下!
- 「勉強するから」と約束してスマホを与えた途端に一切勉強しなくなった
- スマホの使用時間を決めたのに守らず、成績は一気に急降下
3位 夜遅くまでゲームで夜更かし。朝起きられない!
- いくら起こしても起きてこない。毎晩友達とオンラインゲームで夜更かししていたことが判明
- スマホを持たせてから寝る時間が遅くなり、授業中居眠りばかり
こちらもよく読まれています
【中学生】勉強嫌いになる4つの原因とご家庭で出来ること | 家庭教師のえーる
スマホが「学力を破壊する」!? 科学が示す脳への悪影響
「スマホを長時間使用することで、勉強が無駄になる可能性がある」 実は、これは、脳科学研究や教育調査が強く示唆する事実です。ここからは、そんな警鐘を鳴らす、東北大学の川島隆太教授の研究結果についてご紹介します。

川島隆太教授の警鐘:「3時間触ると2時間の勉強がムダに」
「毎日2時間以上勉強しているにもかかわらず、スマホを3時間以上使っている生徒」より、「ほとんど家で勉強しないけど、スマホを全く使わない生徒」の方が、成績が良い
これは、「DS脳トレ」で有名な東北大学の川島隆太教授の調査結果です(2013年、仙台市の中学生対象)
川島教授によると、「スマホを触ること」が、脳に悪影響を与えて、学力を下げてしまうというのです。そして、悪影響の可能性について2つ挙げています。
①記憶の消去と定着阻害
これは、スマホの使用により、せっかく脳に入った学習内容が、記憶に残らない、あるいは、記憶が消去されるということです。
②学習機能の異常
スマホの使用により、脳の学習回路に異常をきたし、新しく知識を習得することが困難になる
「マルチタスク」が集中力を奪い、「小6の脳」で成長停止に!?
川島教授よると、さらに「スマホに多数のアプリを入れている子ほど学力が低くなる」とも。「スイッチング(タスクの切り替え)という心理現象とのこと。
違うアプリの誘惑により注意が削がれ、次々と違うタスクに切り替える行為を頻繁に繰り返すことで、「一つのことに深く集中できる時間が極端に短くなる」ということです。
スイッチングにより、脳の「前頭前野」の発達に悪影響を与え、物事を深く考えられなくなったり、感情がコントロールしづらくなります。 最悪のケースは「小6で脳の成長がとまったまま」になる可能性も。
スマホのしすぎで起こる、学力以外の健康・精神的悪影響
スマホが子どもに与える影響は学力低下だけではありません。
スマホの使いすぎは心身にも悪影響を与え、健康や将来の社会生活に関わる問題になることも。
健康被害と生活習慣の乱れ
- 目の不調
眼精疲労、視力の低下、ドライアイを引き起こすリスクがあがります。
- 身体的症状
スマホを長時間悪い姿勢で見ていることで、スマホ首やストレークネックになる可能性があり、頭痛や肩こりに悩まされます。
- 睡眠不足・自律神経の乱れ
スマホから出るブルーライトによって、睡眠ホルモンの分泌が抑制されます。夜更かしによる睡眠不足や昼夜逆転が起きやすくなります。また、睡眠の質の低下、だるさやめまいなど体調不良を引き起こします。
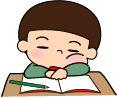
精神面・社会性の問題
- 集中力・忍耐力の低下
短時間で情報が得られたり、スマホの便利さに慣れてしまい、地道な努力ができなくなったり、忍耐性が低くなる可能性があります。
- 感情のコントロール困難
スマホによって瞬時に満たされる快感に慣れ、不快な感情などを我慢できなくなるように。
- SNS依存による弊害
SNS特有の承認欲求「いいね数」により、自己肯定感が増えたり減ったり精神が不安定に。間接的なコミュニケ―ションに慣れ、本来の対面での会話やコミュニケーション能力が落ちやすい。

中学生がスマホと「賢く」付き合うための具体的な方法
今や、スマホはお子さんの生活と切り離せないツールになりました。だからこそ、スマホによる悪影響を少しでも減らし、すくすく育ってほしいですよね。そのためにも、親御さんの協力は不可欠です。
スマホ使用の「ルール」を親子で設定・実行する
お子さんにスマホを持たせると同時に、親子で一緒に必ず「ルール」作りをしましょう。ただし、ルールを一方的に決めたり、押し付けるのはNGです。お子さんが納得し、守れそうな内容にしてあげましょう。
- 「なぜルールが必要か」を説明する
スマホの危険性、学力低下や健康被害などを親子で共有します。どうしてルールを決める必要があるのかを理解してもらいましょう。
- 具体的にわかりやすく
例えば「長時間使ってはいけない」では曖昧過ぎて、お子さんも分かりづらいです。「平日は1日1時間まで」あるいは「21時以降は使用禁止」といったように、具体的なルールにするとわかりやすいでしょう。
- 使用場所を決める
スマホを使う際は、「親の目が行き届くこと」を条件にしましょう。「寝室に持ち込まない」➡「夜更かしを防止」 「スマホをみるのはリビングで」➡「使用時間を把握することで使いすぎを防ぎます」
- 破った場合のルールも決める
これは、意外と決めていないご家庭も多いみたいですが、万が一、ルールを守らなかった場合の、具体的なペナルティも決めておきましょう。
例)「1日スマホの使用禁止」「使用時間の短縮」 など
スマホ以外に「没頭できる何か」を一緒に見つける
「うちの子時間さえあれば、スマホばかり触っている」
このようなお子さんは、もしかすると、「心から没頭できること」が見つかっていない可能性があります。スマホにはゲーム、YouTube、TikTok、など、刺激的で楽しいアプリが沢山入っています。もし、それ以上に「楽しい」「夢中になれる」という体験があれば、スマホに触る時間も短くなるでしょう。
- スポーツや習い事
野球、サッカー、バスケットボール、バドミントンなど、お子さんが興味ありそうなスポーツに挑戦してみる。また、ダンス、ギター、絵画教室、プログラミングなど、やってみたいと思える習い事を始めてみるのもいいですね。これらは、体を動かしたり、達成感、自己表現力が上がる心身共に健康的でポジティブな活動です。
- 自然体験
キャンプ、ハイキング、サイクリング、山登り、釣りなど、自然のなかで五感に刺激を受けられる体験です。
このような体験は、学校外での「学び」になり、子どもたちの経験値をあげ、心も豊かになります。 お子さんに「○○やってみる?」「今度一緒に○○の体験に行ってみようか!」と声をかけてみますよう。
もし、お子さんが好反応をしたな、1日体験などを受けてみましょう。スマホ依存になっている子であれば、そこから抜け出す第一歩になるかもしれません。

【ご家庭の声】スマホ依存を克服し、勉強好きになった事例
息子は中学に入ってからオンラインゲームに夢中になり、時間さえあればスマホの画面を見ていました。成績がどんどん落ちてきたため、私がスマホを取り上げようとすると激しく反発し、親子関係も悪化する一方でした。どうすればいいか悩んでいた時に、知人からえーるさんを紹介してもらいました。
来てくださった男性の先生は、まず息子の好きなゲームを決して否定せず、優しく話を聞いてくれました。苦手な英語と数学は、どこでつまづいたのかを一緒に探して、基礎から丁寧に戻って教えてくれました。先生は息子に『勉強とゲームの両立の方法』を教えてくれたおかげで、息子も納得して勉強するようになりました。親だとついつい頭からゲームを否定して『勉強をさせよう』とするので、逆に反発を喰らいます。でも、先生は、子どもの気持ちも汲み取りながら、うまくやる気にさせてくれるので本当にありがたいです。
先生は、将来ゲーム会社で働きたいという息子の夢に近づくように、一生懸命応援してくださっているし、おかげでモチベーション高く頑張れているみたいです。
中学2年生 Aくんのお母さん
参考文献
- 『スマホが学力を破壊する』これだけの根拠 3時間触ると2時間の勉強がムダに PRESIDENT Online – スマホが学力を破壊する
- スマホ中毒になると「小6の脳」で成長が止まってしまう…東北大の3年間の追跡調査が示す恐ろしい事実 特定のアプリが成績に著しい悪影響を与えている PRESIDENT Online – スマホ中毒になると「小6の脳」で成長が止まってしまう
家庭教師のえーるは、勉強の楽しさから教えます!
- スマホ依存になって全く勉強しなくなった
- スマホばかりみて昼夜逆転して不登校になってしまった
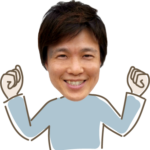 えーる坪井
えーる坪井そのようなお子さんこそ、私たちえーるにお任せください!
やる気が出ない原因の多くは、勉強のやり方がわからないことから起きています。
私達えーるは、相性ピッタリの家庭教師がまずお子さんに勉強のやり方から教えて「わかる!」「できる!」という勉強の楽しさを実感してもらいます!
家庭教師のえーるでは、現在「無料の体験授業」を行っています。
「お子さんのスマホ依存を解消したい!」という方は、この機会にぜひご利用ください!お子さんの成長のキッカケになることを、お約束します。
\ 【関西限定】地元密着26年!家庭教師のえーる /