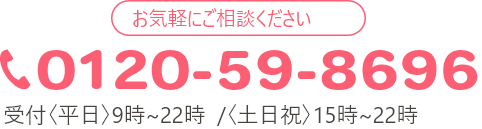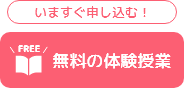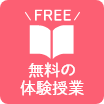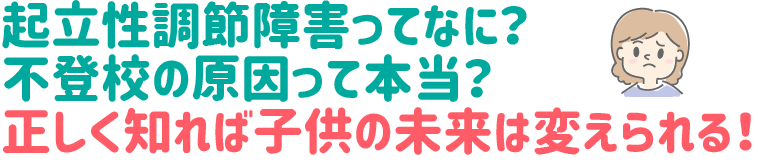
「子どもが朝起きれなくなって、不登校になった…」
「朝になると体調が悪くなり、学校を休む日が増えてきた」
私たち家庭教師のえーるには、近年、不登校の原因として急増している、「起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)」についてのお悩み相談が多く寄せられます。起立性調節障害は、自律神経などの不調で体調不良になり、朝起きれなくなることです。本人の意思とは別に、「朝起きたくても起きれない」「体調が優れない」といった症状が起きてしまいます。そのため「サボり?」「怠けている?」と周囲から誤解を受けやすく、学習の遅れだけでなく、精神的に苦しんでいる子も少なくありません。この記事では、起立性調節障害が不登校につながる理由や、えーるに寄せられる相談事例、対策などをご紹介します。
起立性調節障害(OD)の基本:なぜ朝、体が動かないのか?
起立性調節障害(OD)は、中学生くらいのお子さんに多くみられる自律神経の不調から起きます。午前中に不調の症状が出やすく、午後から徐々に回復し、夕方には元気になるケースは少なくありません。そのため、「本当は元気なのでは?」といった、誤解を生みやすいのです。
「やる気がない」じゃない!起立性調節障害の主なメカニズム
起立性調節障害の症状は、お子さん自身の意思でどうにかなるものではありません。
- 自律神経のスイッチングミス
起立性調節障害のお子さんは、睡眠中に優位になる副交感神経から、起床時に必要な交感神経への切り替えがうまくいきません。
- 脳への血流不足
立ち上がる時に血管が収縮せず、血液が下半身に溜まりやすくなり、脳への血液が行き届かなくなり、めまい、立ちくらみ、倦怠感を起こします。
- 身体の急成長
一般的に、小学生から中学生にかけて身長が大きく伸びますが、急激な成長や、ホルモンバランスの変化により、自律神経の調整がうまくいかず、不調を起こすことも要因です。自律神経の調整機能が追いつかず、不調を引き起こすことも大きな要因です。
登校を阻む朝の主なサイン
- 体がだる・重い
布団から出ようとしても倦怠感が襲い、身体が重く起き上がれない
- 頭痛・腹痛が襲う
朝になると、頭がズキズキ痛くなったり、お腹が痛くなったり吐き気がする。
- 午前中は集中できない
朝からお昼にかけて集中力がなく授業中もぼーっとする。
起立性調節障害が不登校の要因となる深刻な「心の葛藤」
起立性調節障害は体調面の不調だけでなく、精神面への影響も出てきます。
体調が悪い。
学校に行くのも気が重い
その結果不登校になってしまうことも。
学校へ行けなくなるまでの「自己否定の連鎖」
起立性調節障害のお子さんは不登校になるまで以下のような連鎖が起きやすいです。
- 体調不良からの負の連鎖
朝起きれず、遅刻や欠席が増える。授業を受けられなくて勉強が遅れて自信がなくなっていく。
- 周囲との間に溝が生まれる
午前中は倦怠感、頭痛、めまいなど起こす起立性調節障害ですが、午後から回復することが多いため、「なまけもの」「甘えている」など、誤解を受けやすく、心ない言葉を受けて傷つく子も少なくありません。
- 強い自己否定感
「自分だけ勉強が遅れている」「自分がダメな人間」このようになると、自己肯定感が下がってしまいます。
- 「学校=苦痛」な場所
学校に行けないことと、体調不良が続くことで精神的にストレスと受け、学校が苦痛な場所、と刷り込まれていきます。
起立性調節障害で悩むご家庭の新しい相談事例と対策
私たちえーるには、起立性調節障害によっておこる症状以外に、学習困難や進路についてのお悩み相談が多く寄せられます。ここではえーるに寄せられる相談事例や指導についてご紹介します。
事例1:「勉強の空白」をどこから埋めるか?(中3・Kくん)
相談事例(Kくん)
中学3年生のKくんは起立性調節障害の症状に悩み、欠席が続いて勉強の遅れが彼を苦しめていました。
特に苦手科目の理科や社会は、1・2年生の範囲がかなり抜けているため、「これまでの範囲を覚え直すなんて無理!」と、最初から諦めモード。このままでは公立どころか、私立高校の受験も危ういと親御さんからご相談をいただきました。
えーるの指導の視点
- 目標への逆算・重要度学習
私たちえーるの指導は、全てを完璧にやり直すというものではありません。受験で必要な最低限の基礎や、重要ポイントを絞り、優先順位で効率的に学習してもらいます。「捨てる部分」と「確実に取る部分」を明確にし、勉強が中途半端に終わらないようにしています。
- 過去の成功体験の活用
その子が得意だった分野を徹底的に褒め、「できる」という感情を呼び起こすことからスタートします。それによって、自信を失った勉強野の学習意欲を回復させます。
事例2:起立性調節障害で生活リズムが乱れました(中1・Sさん)
相談事例(Sさん)
中学1年生のSさんは、朝、目が覚めても布団から出れず、毎日お昼ごろまで寝ています。お昼からは回復してきて、夕方には別人のように元気な姿になります。元気な時間はずっとスマホを触ってしまい、勉強は全くしません。家にいて運動することもなく、お昼まで布団の中にいるし、体の疲れがほとんどありません。そのため、寝る時間はますます遅くなり悪循環のサイクルです。このままでは高校にも行けないし、ひきこもり状態になってしまうのでは?と、お母さんはかなり心配されていました。
えーるの指導の視点
- 「夜活」の仕組み化と休憩の組み込み
例えば、家庭教師の指導時間を午後7時以降に設定するなど、集中力の高い、夜の時間を最大限に活用します。さらに、25分勉強したら5分の休憩を挟みメリハリをつけて集中しやすくします。
- 夜間の「デジタルデトックス」
まずは、「スマホのない時間」をつくり、勉強に集中しやすい環境をつくります。指導時間だけでなく、「21時以降はスマホを親が預かる」「寝室にスマホを持ち込まない」など、乱れ気味の生活習慣を一旦リセットしてもらいます。最初のうちは慣れないかもしれませんが、慣れてくると、「別になくても困らない」と、これまでスマホに依存していたことに気づきます。親御さんにも協力してもらい、一緒にデジタルデトックスを成功させ、元の生活習慣に徐々に取り戻していきます。
起立性調節障害のお子さんを支える!えーるの柔軟な学習サポート
私たちえーるが考える、起立性調節障害を持つお子さんへのサポートは「体調を最優先に、柔軟に学習を」です。
お子さんの体調に合わせた「オーダーメイド指導」
- 指導時間の柔軟な設定
起立性調節障害のお子さんの多くが午前中や日中に体調を崩しています。お子さんの体調が安定してくる夕方、もしくは夜に指導を行います。また、お子さんの体調などに合わせて、日時の変更なども柔軟に対応します。
- 疲労度に応じた学習メニュー
「結構しんどそうやし、この問題までにしようか」
「今日は得意な問題だけにしようか」
起立性調節障害の症状の度合により、お子さんの体調や、気分に合わせた無理のない指導を心がけます。
心の安心基地となる「相性の良い先生」との出会い
- 「自分をわかってくれる」という安心感
私たちえーるの先生は、起立性調節障害の症状に関して、決して否定をしません。「それはしんどいね」「あなたのせいじゃないよ」と、お子さんに共感し、家庭教師が「心の安全基地」になることを目指します。
- 信頼できる「伴走者」
私たちは、お子さんの勉強のサポートだけでなく、勉強以外の心配事や、悩みを相談してくれる子も多いです。悩みは話を聞いてあげるだけでも効果抜群。不安がなくなることで、勉強に集中しやすくなります。
最新科学が示す!自宅でできる改善策「水分補給」と「運動療法」
起立性調節障害の症状改善には、日常生活の中で取り入れられる科学的根拠(エビデンス)のあるアプローチが有効です。
血液量を増やす「適切な水分摂取」
起立性調節障害のお子さんにとって、十分な水分補給は、体内の血液量を増やし、血流を安定させる効果が期待できます。
- 目標量の設定: 1日800ml~1.5Lの水分摂取を目標とします。
- 朝のルーティン: 特に、朝目覚めてすぐにコップ1~2杯(約200~400ml)の水を飲むことが推奨されています。冷たすぎない常温の水が理想的です。
負担を抑えた「段階的な運動療法」
起立性調節障害のお子さんは、適度な運動をすることで自律神経の働きを安定させる効果があります。
- 臥位(横になった姿勢)から始める
リカンベントバイクなど、横になった姿勢でできる運動から始めることで、身体への負担を最小限に抑え、安全に体力と自律神経機能を向上させます。
- 関西医科大学の知見
関西医科大学総合医療センターでも、OD起立性調節障害の症状改善に非常に有効なアプローチとして、リカンベントバイクを用いた臥位での運動療法が積極的に推進・研究されています。
- 継続的な取り組み
無理なく継続できるペースで、少しずつ運動強度を上げていくことが大切です。
(参考記事:関西医科大学 総合医療センター「ODの運動治療」および、日本小児心身医学会 起立性調節障害診断・治療ガイドライン(2023年改訂版)など)
(参照:一般社団法人起立性調節障害改善協会HP「起立性調節障害から『不登校』になることはある?」など)
一般社団法人起立性調節障害改善協会HP参照
この記事もよく読まれています
>>不登校生サポート
無料体験授業で、これらの勉強法をすべて教えます!!
お忙しい中、最後まで読んでいただきありがとうございました。正直、「うちの子ほんとにできるのかな??」と思っている方も多いかと思います。
 えーる坪井
えーる坪井そこで!家庭教師のえーるは無料の体験授業をおこなっています!
無料体験でこんなに学べる!
- 1日15分!勉強嫌いな子でも毎日つづく予習復習法
- テストの点数がバッチリとれるテスト勉強のやり方
- 弱点や基礎へもどれるのカンタン戻り法
無料の体験授業は、なんとじっくり120分!受けられた方からは、嬉しい喜びの声を沢山いただいています。
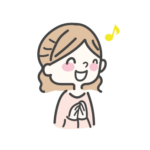
この勉強法ならうちの子にもできそう!♪
えーるの体験授業でピッタリの”勉強のやり方”をお伝えしています。「成績アップのきっかけ作り」を、ぜひ私たちにお手伝いさせてください!
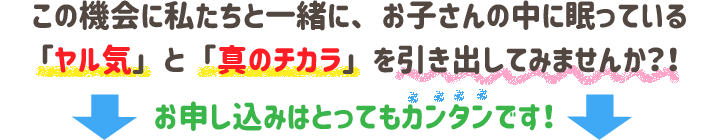

\ 24時間いつでも受付!簡単1分で完了! /
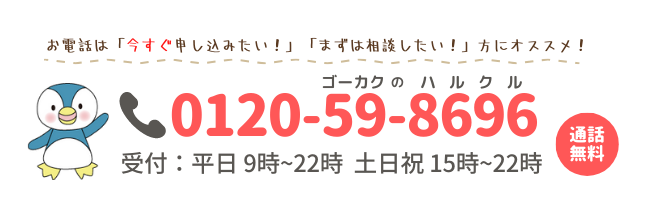
24時間OK!専門スタッフにお気軽にご相談ください!
※体験授業を受けてみて少しでも「思っていたのと違った…」そう思われた方は遠慮なくお断りください。
お子さんがやる気になり、勉強のやり方もピッタリだと思われたときだけ、私たちはお力になりたいと思っています。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。
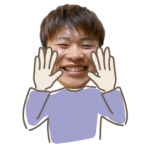 つばさ先生
つばさ先生それでは、体験授業でお会いできることをスタッフ一同、楽しみにしています!